千葉 八千代市
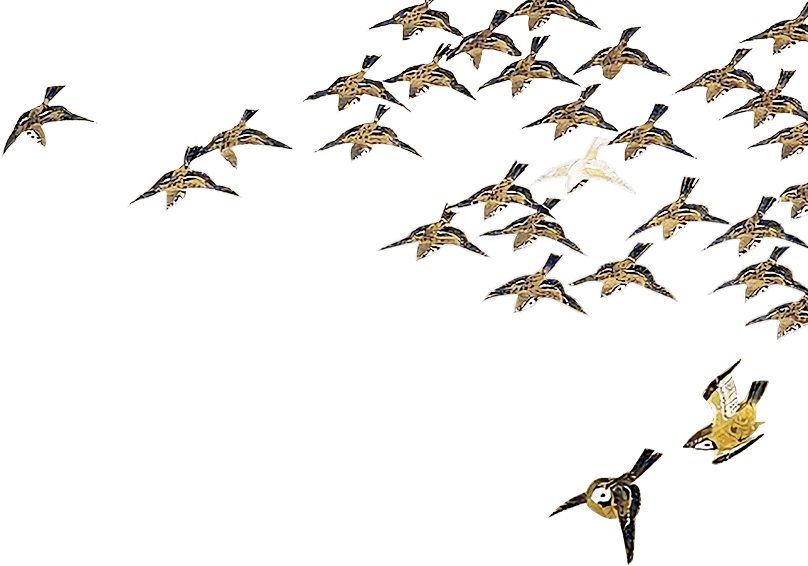
検索結果一覧

 時平神社
時平神社- 八千代市大和田793

 飯綱神社
飯綱神社- 八千代市萱田476

 高津比咩神社
高津比咩神社- 八千代市高津294

 米本神社
米本神社- 八千代市米本1641
 八幡神社
八幡神社- 八千代市吉橋1195
 諏訪神社
諏訪神社- 八千代市八千代台西9-3-15

 神明神社
神明神社- 八千代市村上1648

 時平神社
時平神社- 八千代市萱田町947

 根上神社
根上神社- 八千代市村上南1-15-1
 神明社
神明社- 八千代市大和田新田963
 観音寺
観音寺- 八千代市高津1347
 貞福寺
貞福寺- 八千代市吉橋804

 七百餘所神社
七百餘所神社- 八千代市村上433・434

 八坂神社
八坂神社- 八千代市下市場1-24号
 大和
大和八幡神社 - 八千代市勝田1255-2
 熱田神社
熱田神社- 八千代市佐山1921
 長福寺
長福寺- 八千代市米本1587

 稲荷神社
稲荷神社- 八千代市勝田台北1-23-21

 日枝神社
日枝神社- 八千代市麦丸1336
 光明山
光明山善福寺 - 八千代市米本2077-1
 一進寺
一進寺- 八千代市大和田新田350-4
 香取神社
香取神社- 八千代市保品812
 円光院
円光院- 八千代市大和田785
 勝田寺
勝田寺- 八千代市村上1735-89
 厳島神社
厳島神社- 八千代市村上1522
 熊野神社
熊野神社- 八千代市桑橋910-2

 白籏神社
白籏神社- 八千代市下市場2-7-15
 駒形神社
駒形神社- 八千代市上高野283
 浅間神社
浅間神社- 八千代市南村上2-25-1

 薬師寺
薬師寺- 八千代市萱田町1060-1
地域の祭り・行事一覧(2025年度)※
地域の新着口伝
 投稿日:訪問日:
投稿日:訪問日: 薬師寺|八千代市 “地域の歴史を語る寺”
薬師寺|八千代市 “地域の歴史を語る寺”成田街道沿いにあります。寂れてはいるが、旧家の方々が管理なさっていると思われます。そういった旧家の方々が地域の歴史を作ってこられたことを想像しながらお参りさせて頂きました。境内にこちらの住職さんと檀家の方々で四国遍路をなさった記念碑があり、最年長者確か90歳前後で驚きました。
 投稿日:訪問日:
投稿日:訪問日: 根上神社|八千代市 “根上神社由来”
根上神社|八千代市 “根上神社由来”根上神社古墳(ねのかみじんじゃこふん)。
場所:千葉県八千代市村上南1-15-1(「根上神社」の住所)。東葉高速鉄道東葉高速線「村上」駅の北、約170m。国道16号線沿いにあるホームセンター「ジョイフル本田 八千代店」の南東側。駐車場有り。
「根上神社古墳」は、八千代市では最大の前方後円墳で、全長約50m、前方部幅約32m、後円部径約35mの大きさ。発掘調査は行われていないが、6世紀頃のものと推定されている。南東向きの古墳で、北西側の括れ部分に「根上神社」が鎮座しているため、その名がある。「根上神社」の由緒は不明であるが、祭神は大己貴命で、国土開発の神である。あるいは、「子の神(ねのかみ)」から鼠~大黒天(大黒様)~大国主神と連想して、祭神を定めたのかもしれない。 投稿日:訪問日:
投稿日:訪問日: 時平神社|八千代市 “時平神社由来”
時平神社|八千代市 “時平神社由来”時平神社四社(ときひらじんじゃよんしゃ)は、千葉県八千代市にある四つの時平神社の総称である。下総三山の七年祭りにもかかわりが深い。御祭神はいずれも左大臣藤原時平。
平安時代初期、時平は若くして左大臣まで登り栄達するが、菅原道真を太宰府に左遷させた張本人とされる。道真が左遷先で亡くなる、ほとんど直後というタイミングで、自身も39歳の若さで死去。
その死は当然のことながら道真の祟りと囁かれた。ある意味では、日本における天神信仰の確立を担ったことになる。
四社ともいずれも由緒や情報に乏しく、なぜこの地域に四社もの時平神社が集中しているのか不明。特に、大和田は慶長15年(1610年)に、萱田町は元和元年(1615年)に、それぞれ江戸初期に相次いで創建している。
当地域には、時平はじめ親族が次々と亡くなってしまう状況に対して悲観した、時平の妻子や一族が当地に移り住み、特に時平の娘である高津姫の伝承が残されている。それが同市内に鎮座する高津比咩神社につながる。
当地域はまた、菊田神社に代表されるように、平安時代末期に流罪となった藤原師経・藤原師長の上陸地にも近く、当地で祖先の時平を奉斎したとも伝わり、時平に対する信仰はもともと厚い地域柄ではある。下総三山の七年祭り(千葉県指定文化財)
数えの七年目ごとの丑年と未年に行われる船橋市、八千代市、千葉市、習志野市の4市・9社にまたがる壮大な祭りです。
その年の9月13日に小祭が営まれ、続いて11月の上旬に船橋市三山の神揃場(かみそろいば)から二宮神社にいたる神輿の昇殿参拝と千葉市幕張の磯出式を中心とした二日間にわたる大祭が営まれます。
この祭りの伝説は、藤原時平の子孫が久々田(習志野市津田沼)に流れ着き、深山(三山)に住み着いた後二宮神社の神主になり、また、高津には時平の娘が住み着いたというものです。祭りに参加する9社には役割があり二宮神社(船橋市三山)は夫・父、子安神社(千葉市畑)は妻・母、時平神社(八千代市大和田・萓田町)は息子・長男、八王子神社(船橋市古和釜)は末息子、高津比咩神社(八千代市高津)は娘、菊田神社(習志野市津田沼)は伯父、大原大宮神社(習志野市実籾)は伯母、子守神社(千葉市幕張)は子守、三代王神社(千葉市武石)は産婆に当たると考えられてきました。
地域の記事
- - Yahoo!ニュース高津比咩神社の杜で新年の運試しも「Mabuhaymarche プチマルシェ」5日に開催!




 かおりちゃん
かおりちゃん




 マルちゃん
マルちゃん
 haru nohara
haru nohara
 ききょう
ききょう


 ぐっさん
ぐっさん